これは、お釈迦さんの最晩年の頃の話で、身の回りのお世話をしていた弟子のアーナンダさんが登場します。
齢八十歳となったお釈迦さんの最後の旅路における出来事を記したエピソードです。
エピソード(長阿含経巻第2「遊行経」)
一年の中で最も雨の降る季節となった頃、お釈迦さんは病気にかかってしまいました。それは全身に痛みを感じるほど辛いものでした。
しかしお釈迦さんは、その痛みにじっと耐え忍んでいました。
「病気のせいか……、身体が痛む。でも弟子達は各地にいて、ここには今ほとんどいない。彼らに別れを告げぬまま、死ぬわけにもいかない。今はなんとかして病苦に耐え、命を繋ぎとめなければ……」
そう思ったお釈迦さんは、一人静かな場所に移り、じっと座っていました。そうすることで、少しは痛みが鎮まるようでした。
その時、病気になったお釈迦さんの様子を心配していたアーナンダさん。お釈迦さんが静かに座っている姿を目にし、彼はすぐさま近づいて言いました。
「今、お顔を拝見したところ、元気そうに見えるので少し安心致しました」
そう言うと、彼はその場に座りました。
「師匠。あなたが病気だと知って、私は何も手がつきませんでした。眼の前が真っ暗になりました。師が説いて下さった教えも何もかもが吹き飛んでいました。
しかし今、かすかな希望を見出しました。私達が不安に思う中、師が何も教えを説かずに亡くなられるはずはないと」
それを聞いたお釈迦さんは、彼に対し、こう言いました。
「アーナンダ。弟子の皆が、私に何を期待するというのですか?
もし私が弟子達の上に立ち、導いてくれると思っている者がいるなら、何か語ることがあると思うかもしれません。しかし私は弟子達の上に立ち、導こうなどとは思っていません。
私は今までずっと、心の内に留めることもなく、そして誰彼、別け隔てなく、法を説いてきました。誰にも言わず、内に秘めたままの教えなんてありません。
そんな私が、一体弟子達にこれ以上何を説くというのですか?
しかも私は随分、年を取りました。もう齢八十歳です。至るところ修理して、何とか動いているオンボロ車のような身です。
ですからアーナンダ。自らを灯明とし、法を灯明としなさい。他を灯明とするのではありません。
自らを拠り所とし、法を拠り所としなさい。他を拠り所とするのではありません。
それは何故かというとですね。アーナンダ。あらゆるものごとは、それぞれありのままで、真実のありようを伝えている。
だから僧侶たるもの、この身、心、感覚、そして様々な物事を、熱心かつ冷静に、また注意深く観つづけ、どう生きるかを考えねばなりません。
私が亡き後も、自らを灯明とし、法を灯明とし、他を拠り所とせずにいる者は、私の最上の弟子となるに違いありません。誰でも絶えず学ぼうと努める者は……」
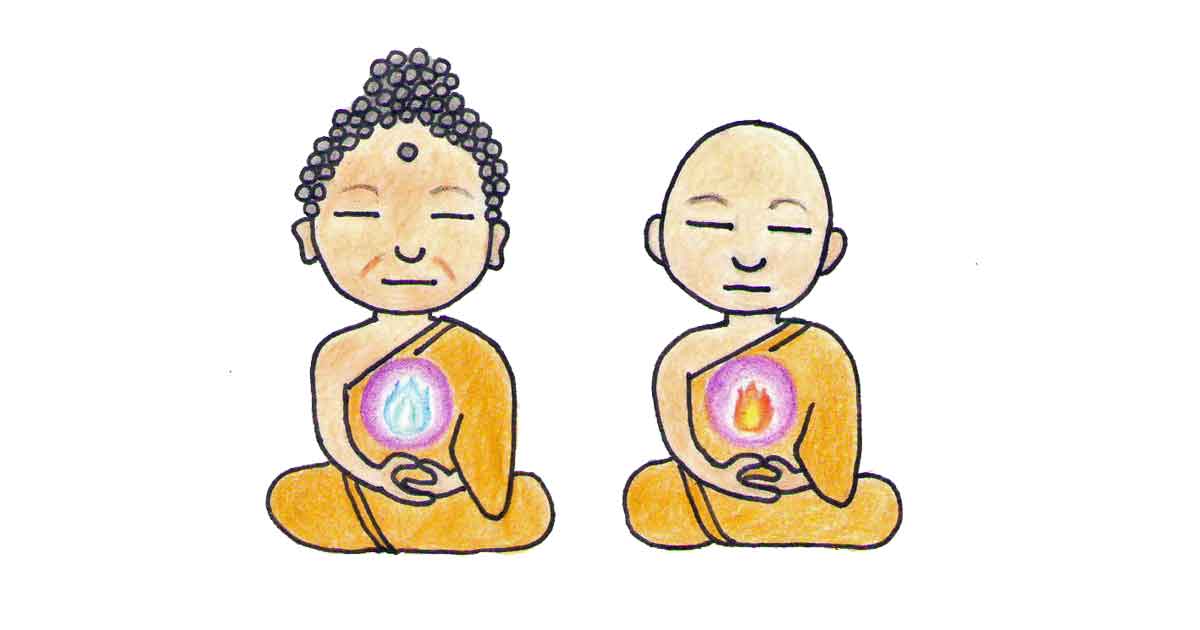
メッセージ
「自灯明法灯明」と言われる有名な話で、お釈迦さんの遺言として伝えられています。パーリ原典では灯明ではなく、島を意味する言葉が使われています。
暗闇の中、道を示してくれる灯火。そして、どんな流れの中でも決して揺るがない島。つまり、どちらも「拠り所」を表しています。
アーナンダさんにとって、お釈迦さんは自分の人生に無くてはならない存在だったのでしょう。彼は、お釈迦さんがいなくなってしまうことをとても恐れていました。
他にも、彼が「死なないでください!」とお釈迦さんに懇願する話や、お釈迦さんが亡くなるであろうことを想像して号泣している話が、お経には書かれています。
きっとお釈迦さんがいない人生なんて想像していなかったのでしょう。
彼にとって、お釈迦さんはまさしく、拠り所だったのだと思います。
そんな彼に対するお釈迦さんの言葉はとても印象的です。
「他を拠り所とするのではなく、自らを拠り所に、そして法を拠り所としなさい」
私自身、ひどく悩んだ時期がありました。人は本当に苦しみに追い込まれると、やはり何とかしたいと思うものです。しかし、どうしていいのかがわかりません。
そんな中、私はその苦しみを解決すべく、もがきながらその答えを探しました。
世の中には目を向けると、たくさん答えが用意されています。ものによっては、言ってることの意味はわかりました。また、同意できることも確かにありました。
しかし、その答えはどれも、自分にはどうもしっくりきませんでした。
「決定的に何かが足りない」と、いつも心のどこかに、そんなわだかまりがありました。それは仏教と言えど、例外ではありません。
よく信じる者は救われると言いますが、私には、これが全く当てはまらなかったのです。
特別な何かを拠り所としようとすると、いつもそれが自分とは関係のない遠くのことに思えました。何かを信じ切るということが、私にはできませんでした。
どんなに素晴らしい答えも、それはその人の答えであって私の答えではありません。もちろん参考になりますが、最終的に苦しみから救うのは他ならぬ自分自身です。
だから、私自身の答えを見つけなくてはいけませんでした。
しかしそんな中で、気付いたことがありました。
私は他の何かに答えを求めようとして、肝心の苦しんでいた自分自身を置き去りにしていたということです。
苦しんでいる自分自身を見失ってしまっていては、そこからどうしたらいいのかもわかりません。自分が今どこにいるのか知らなければ、どちらの方向に進むべきなのかもわかりません。
私はここに何か苦しみを解決する糸口を見つけた気がしました。
「では一体自分って何なんだろう……?」と改めて自分を見つめると、自分のことをわかっているつもりで、実は全然わかっていない自分がいました。
ただ、自分と一言といっても、いろんな自分がいます。
そこには、目を背けたくなる自分もいれば、無意識に見ないようにしていた自分もいました。反対に自分でも驚くような自分もいました。
でも間違いなく、どれも紛れもない自分でした。
自分に目を向けるということは、信じ切れば見えなくなってしまいます。その反対に端から疑ってしまえば目を逸らそうとします。
実につかみどころがないものです。
しかし、そこからたくさんのヒントを見つけたのも、また事実です。
何も他に探しまわらなくても、誰にとっても一番身近にある自分に目を向ければ、そこにはたくさんのヒントが転がっていました。
ですから、このエピソードのお釈迦さんの言葉は、意外なようで妙に納得がいきます。
さて、それでは、自分が拠り所であるならば、私は他には頼ることなく生きているのか?
決してそんなことはありません。私が生きる上では、様々なものに頼って生きています。
空気が無ければ呼吸もできず、水が無ければ渇き、生物がいなければ食べる者も無く、飢え死にます。人がいなければ、私はこのように文章を書くことすらありません。
人は生きる上で、様々なものに頼っています。そういう事実も、自分を見つめれば必然的にくっついてきます。この事実の下で生きている自分も、間違いなく自分ですから。
そこで重要になってくるのが法灯明です。ただ、法というと、如何にも仰々しく特別なものとして見られがちですが、私は自灯明も法灯明も、実はあまり違いがないと思っています。
自分は誰にとっても一番身近にあるもので、特別なものではありません。ですから法もまた、特別なものではないと思います。
法については、別の話題になりますので、詳しくは次の機会に回したいと思います。

2013年11月


